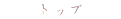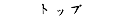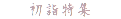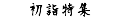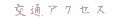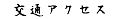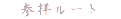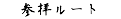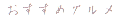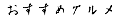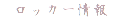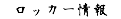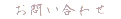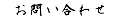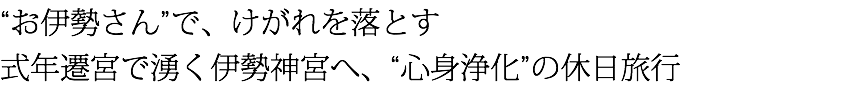

週末リゾートを兼ねた伊勢の旅2日目の日曜は、いよいよお伊勢参りだ。「伊勢志摩ロイヤルホテル」の露天温泉岩風呂に浸かって目を覚まし、伊勢神宮へと向かう。その途中に立ち寄ったのは、ホテルから車で20分ほどの伊雑宮(いざわのみや)。訪れてみると、民家の並び、こんもり茂った緑の中に佇む、小ぢんまりとした神社である。観光客が多く訪れるような場所ではなく、近所の人々とともにあるような社だ。ここは、伊勢神宮の別宮。伊勢神宮には、正宮である「内宮」「外宮」のほか、別宮や摂社、末社など125社の神社があり、これら全部を含めて「伊勢神宮」なのだ。
125社の中で、正宮の内宮と外宮に次いで尊いとされるのが別宮で、伊雑宮もその別宮の1つ。さらに、伊勢神宮の中で天照大御神を祭るのは、内宮を含め3社しかなく、その1社が伊雑宮なのである。実はこの小さな神社は、“お伊勢さんファミリー”の中では、かなり重要な神社なのだ。
そんな由緒ゆえ、身を引き締めて参道を進むと、内宮と同じ造りのシンプルな本殿が見えてきた。シンプルとは言っても、あまりの格式の高さのために他の神社では採用されていない「唯一神明造」。そんな貴重な建物が、内宮のように高い板垣に遮られるでもなく、簡素な柵に囲まれただけでありのままに建っている。これは畏れ多いと思いながら、本殿に向かって手を合わせる。
別宮である伊雑宮も、内宮や外宮同様に20年ごとの式年遷宮が行われ、2014年に予定されている。また、皇女である倭姫命(やまとひめのみこと)が伊勢神宮へ供える神饌(しんせん)を探していた際に見つけた場所という神話に基き、伊雑宮は伊勢神宮の別宮では唯一、神田を持つ。毎年6月24日に行われる神事の御田植式は、日本三大御田植祭の1つ。やはり、格調高し、なのである。伊雑宮だけでも十分にパワースポットだが、いよいよこの後は伊勢神宮の“中枢”に向かうことにした。
お伊勢参りは、外宮から参拝をするのが習わしだと聞いたので、伊雑宮から車で40分ほどの外宮に到着。さすがに参拝客であふれている。ただでさえ参拝客が多い場所であるうえ、式年遷宮で大きな注目を集めているのだ。
20年ごとの式年遷宮は、伊勢神宮の数多い神事の中で最も神聖かつ重要なもの。内宮と外宮、別宮の社殿を、隣接する敷地に新たに造り替え、ご神体だけでなく、装束や神宝も造り替えて新社殿にお移りいただく行事だ。いわば“神様のお引っ越し”である。奈良時代の天武天皇の御発意で、次の持統天皇の時代、690年に第1回目が行われた。以降、戦国時代の中断期をはさみ、1300年余にわたって続いている。2013年が62回目だ。
20年ごととはいっても、最初の準備となる、用材伐採のための安全祈願の神事は2005年に始まっている。その後も数々の神事が行われているため、1回の遷宮は8年がかりだ。
そもそも、なぜ遷宮をするのか、そしてなぜ20年ごとかについては、今となっては明確ではないという。老朽化を止めて浄化する、20年間隔は技術の伝承がしやすいなど、多くの説があるが、すべて推測。ただし、20年ごとに行われる結果、伝統建築の技法が寸分違わず伝承されてきているのは確かだ。日本の伝統の継承という意味では、とても重要な行事なのである。
左側通行の火除橋(ひよけばし)を渡って参道を進み、第一の鳥居、第二の鳥居をくぐると御正宮。囲いで覆われて神明造の屋根しか見えないものの、新旧2棟の神殿が並び建っているのが分かる。
正宮前は、さすがにすごい人だかり。他の参拝客同様、静かに合掌する。外宮の祭神は豊受大御神(とようけのおおかみ)。天照大御神の食事である御饌(みけ)をつかさどる神様である。その後、境内の別宮である多賀宮(たかのみや)、土宮(つちのみや)、風宮(かぜのみや)を順に参拝。これらの別宮も、翌年には作り替えられる予定だ。何と大掛かりなことかと思いながら、外宮を後にする。次は内宮だ。
外宮から内宮までは、およそ5kmであり、歩けない距離ではない。参拝客の多さは外宮と変わらない。神域への架け橋となる宇治橋を渡って参道へ。外宮の参道はうっそうとした森の中を通っていたが、内宮の参道は広々として開放的だ。
第一の鳥居をくぐったところで、多くの人が、境内の横を流れる五十鈴川に手を浸しているのに気づく。聞けば、手水舎の代わりなのだという。内宮には、通常の神社で目にするような手水舎があるが、本来は川の水で手を清めて正殿にお参りするのが正しい姿なのだとか。ならばと、自分も清らかな流れに手を浸す。
続いて第二の鳥居をくぐり、参道の突き当りまで行くと、そこにあるのが内宮の正宮。さすがに、周囲はうっそうとした木々に囲まれている。20段ほどの石段の上に建つ神殿は、玉垣と御幌(みとばり)に遮られて見ることはできない。が、ここの祭神は天照大御神。皇室の御祖神(みおやがみ)で、日本国民の氏神でもある。そう聞くだけで、言い知れぬパワーを感じる気がする。
正宮の参拝を終えた後は、外宮と同じように、境内の別宮で天照大御神の荒御魂を祭る荒祭宮(あらまつりのみや)、風日祈宮(かざひのみのみや)を参拝。
参道を戻りながら、ふと思う。伊勢神宮には正宮に次ぐ格式の別宮が、全部で14社ある。自分は今日1日だけで、そのうちの6社に参拝したのだ。内宮と外宮の2つを合わせると、8つの社に参拝したことになる。これまでの人生で、これほど多く手を合わせたことなどない。さすがにけがれも落ちただろう。だが、信心深い人の中には、伊勢神宮125社すべてに参拝する人も多いという。上には上がいるのである。
かくいう自分のお伊勢参りも、まだ終わらない。門前のにぎわいにも身を浸さねばならないのだ。訪ねるは、内宮門前のおはらい町である。
内宮の門前町であるおはらい町は、お伊勢参りが庶民の間で盛んになった江戸時代に、全国から集まった参拝者をもてなした場所。宇治橋から五十鈴川に沿って続く石畳の通りには、昔ながらの切妻・入母屋・妻入り様式の家屋が軒を連ねている。
まるで原宿の竹下通りのような人混みの中を、ぶらぶら散策する。おはらい町の中心部には、江戸時代から明治時代にかけての街並みや店舗を再現した「おかげ横丁」なるものもある。食事どころに喫茶、土産物屋。なかでも伊勢土産の定番である「赤福」の本店には、観光客が鈴なりだ。
「伊勢うどん」「松阪牛」「伊勢エビ」などの幟(のぼり)もあちこちに見える。そういえば空腹だ。ということで、うどんを味わうことにする。伊勢うどん専門店の「岡田屋」に入り、出てきたのは、太めの麺につゆをからめた、一見“ぶっかけ”のようなもの。つゆが黒々として、何だか辛そうである。が、一口食べて、ふわっとした甘さに驚く。麺にまったくコシがないので、つゆとよくからみ、自分が想像していたうどんとはまったく別物と言いたいほど。これはうまい!
うどん1杯では少し物足りないかと感じつつ、さらにおはらい町を歩くと、目についたのが1軒の酒蔵。「伊勢萬」の名のついたこの酒蔵では、伊勢唯一の地酒が味わえるらしい。五十鈴川の伏流水で作ったという「おかげさま」だ。試飲ができたので、しぼりたての生原酒を一口だけもらう。すっきりとした淡麗ながら、ほのかに甘さを感じる酒だ。生ゆえに持ち帰り不可の試飲限定だが、生原酒でなければ販売されているので、土産に買っていくことにしよう。そう思って隣のATMでお金を下ろしたら、明細書の裏のおみくじに“大吉”の文字が。店の人に聞くと、大吉はめったに出ないらしい。お伊勢さんの門前らしい“ご利益”に感謝!
大吉も引き当てたことだし、奮発して松阪牛でも食べようかと思ったが、参拝で神聖な気分になった後に、たらふく食べてしまうのはいかがなものだろう。迷いながらガイド本を開くと、ありがたい一文を発見。神事の後には、神様に捧げた神酒(みき)や神饌(しんせん)を飲食する直会(なおらい)という行事がつきもので、参拝後におはらい町で飲食することにも、直会の意味があるというのだ。なるほど。ではさっそく自分も直会だ。というわけで、松阪牛の幟を掲げた「おく乃」で、松阪牛の膳を食す。柔らかい肉はまさに“ふわとろ”でジューシー。お伊勢参りの最高の締めくくりである。
気持よく腹を満たし、帰路につく。的矢湾を臨むリゾートでくつろぎ、お伊勢参りでけがれを落とす週末の、何と充実していたことだろう。体の疲れも取れ、心もずいぶん清々しく感じるのは、浄化されたからだろうか。式年遷宮が無事に終了した後、機会があれば、伊勢志摩の漁村巡りや、生まれ変わった内宮と外宮を含む伊勢神宮125社巡りなども楽しんでみたい。今回宿泊した伊勢志摩ロイヤルホテルを拠点にすれば便利だろう。
JAGZY 2013年10月21日 「“お伊勢さん”で、けがれを落とす 式年遷宮で湧く伊勢神宮へ、“心身浄化”の休日旅行」より引用
『伊勢神宮』関連記事で下調べ
(c) isejinguusyoshinsyatoranomaki