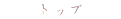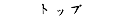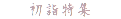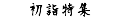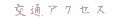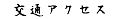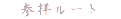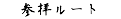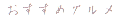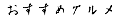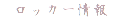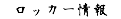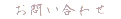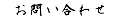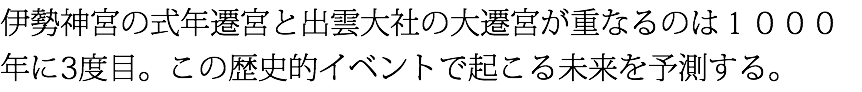

20年に一度のペースで執り行われる伊勢神宮の『式年遷宮』が2013年の今年10月に内宮、外宮ともに行われる。しかし今年はこの伊勢神宮の式年遷宮に重なってもうひとつの一大行事が執り行われる。それが出雲大社の大遷宮なのだ!縁結びの神様として知られる出雲大社だが、伊勢神宮と並びパワースポットとしても近年訪問者が増加している。
こんな大行事が一度にくる2013年という年がどんな年になりうるのか?過去のデータも含め未来を予見してみたいと思います。過去の伊勢神宮の式年遷宮と出雲大社の大遷宮が重なった年を検証します。(参考:SPA!10月1日号)
20年に一度のペースで執り行われる伊勢神宮の『式年遷宮』が2013年の今年10月に内宮、外宮ともに行われる。しかし今年はこの伊勢神宮の式年遷宮に重なってもうひとつの一大行事が執り行われる。それが出雲大社の大遷宮なのだ!縁結びの神様として知られる出雲大社だが、伊勢神宮と並びパワースポットとしても近年訪問者が増加している。
こんな大行事が一度にくる2013年という年がどんな年になりうるのか?過去のデータも含め未来を予見してみたいと思います。過去の伊勢神宮の式年遷宮と出雲大社の大遷宮が重なった年を検証します。(参考:SPA!10月1日号)
大発展の礎となった1610年と1954年!(伊勢神宮と出雲大社の同時遷宮を終えた翌年)
最初の1610年は江戸時代の初期。長く続いた戦乱の世、戦国時代を終え戦のない世の中がスタート、政治も安定し長期に渡る徳川政権の礎が作られた時期なのです。この1610年に発見された足尾銅山が産出する銅は、当時の主要な輸出品となった。徳川家康は鉱山の掘削のために西欧の技術を導入し、後の掘削の技術や測量の技術を革新的に進歩させることになるのです。その後訪れる明治維新後の欧米列強の仲間入りを果たすための資金の蓄積や西洋技術を取り入れる基盤はこの1610年に始まっていたのです。そんな近代日本のスタートの年となったのがこの1610年と推察されます。
そして2回目の同時遷宮を終えた1954年は太平洋戦争の敗戦から9年目の年、この年も1950年に勃発した朝鮮戦争による特需で戦後復興の礎を作ることとなった年です。過去経験をしたことのないほどの好景気(神武景気)が訪れこの10年後には日本初の東京五輪を経験し、戦後の焦土から日本は世界第2位の経済大国へと上り詰めて行く事になるのです。
そして2014年を占うと、アベノミクスによる経済の好転の兆し、富士山の世界遺産登録、そして7年後の東京五輪の決定。とバブル崩壊、東日本大震災以来長く続いた不況、不遇に喘ぐ日本にもたらされる上昇気流の兆し。この3度目の同時遷宮のタイミングを新たな日本のスタートの年として験担ぎをしてみても良いのかもしれません。
『伊勢神宮』関連記事で下調べ
(c) isejinguusyoshinsyatoranomaki